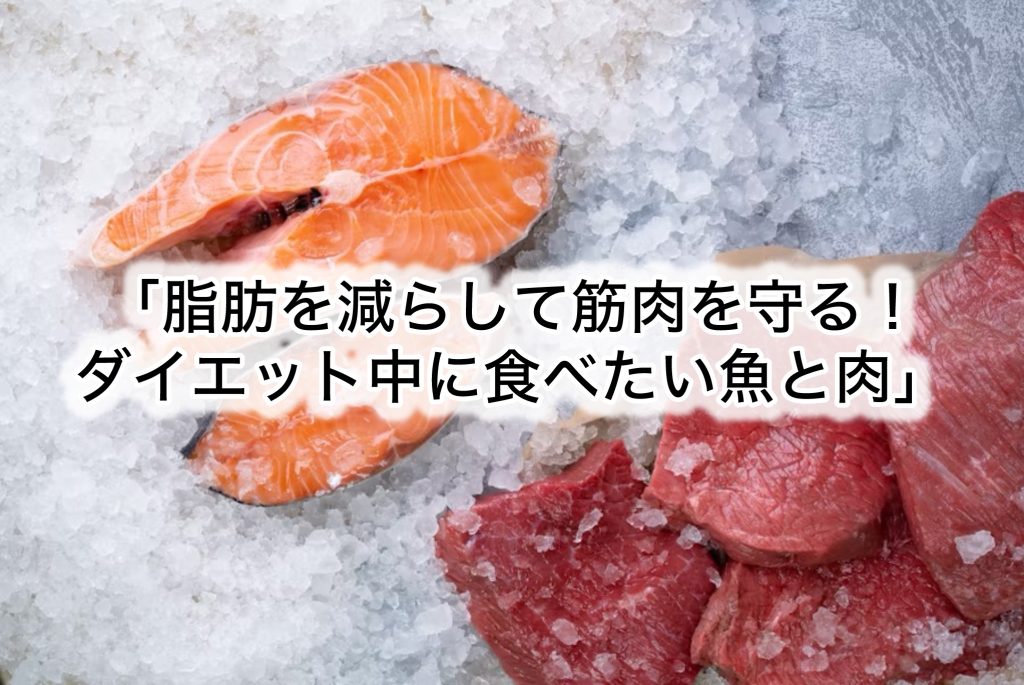「脂肪を減らして筋肉を守る!ダイエット中に食べたい魚と肉」
BLOG
2025 / 08 / 08
最終更新日:2025年8月13日

ダイエットを経験したことがある方なら、「ただ食事量を減らすだけ」では長続きしないことを、身をもって知っているはずです。
特に30〜50歳になると、20代の頃と比べて基礎代謝が低下し、筋肉量も減少傾向にあります。
そのため、食べる量を減らし過ぎると筋肉が落ちやすく、リバウンドしやすい体質になってしまうのです。
Contents
ダイエットの目的とリスクを再確認する
多くの人は「体重を落とす」ことをダイエットの目的としがちですが、本質はそこではありません。
本当の目的は、健康的で引き締まった体を手に入れること。
そのためには、単純な体重減少ではなく、体脂肪の減少と筋肉量の維持が必須です。
特に30〜50歳は、以下のリスクが高まります。
- 筋肉量の減少 → 基礎代謝が下がり、太りやすい体質に
- 骨密度の低下 → 運動不足や栄養不足による骨粗鬆症リスク
- ホルモンバランスの変化 → 男性はテストステロン低下、女性は更年期による代謝低下
これらを防ぐためには、必要な栄養を摂りながら脂肪を落とすことが重要です。
筋肉を落とさず脂肪を減らすためのPFCバランス
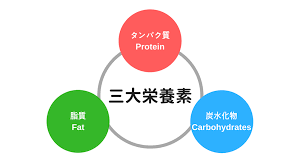
ダイエット経験者でも意外と見落としがちなのが、PFCバランス(タンパク質・脂質・炭水化物の比率)です。
基本の目安(30〜50歳・活動量中程度の場合)
- タンパク質:体重 × 1.5〜2.0g
- 脂質:総摂取カロリーの20〜25%
- 炭水化物:残りのカロリー分
例:体重70kgの男性(目標カロリー1,800kcal)の場合
- タンパク質:105〜140g(420〜560kcal)
- 脂質:40〜50g(360〜450kcal)
- 炭水化物:200〜230g(800〜920kcal)
ポイントは、タンパク質を優先的に確保すること。
これにより、筋肉の分解を防ぎ、基礎代謝を保ったまま脂肪燃焼を促進できます。
魚と肉がダイエットに適している理由

魚と肉は、ダイエット経験者にこそおすすめしたい食材です。理由は大きく3つあります。
- 高たんぱくで筋肉を守る
魚も肉も、筋肉の材料となるアミノ酸を豊富に含みます。特に鶏胸肉や白身魚は低脂質で、カロリーを抑えながらタンパク質を摂取可能。 - 満腹感が持続しやすい
タンパク質は消化吸収に時間がかかるため、血糖値の急上昇を防ぎ、間食を減らせます。 - 脂質の質が選べる
魚の脂はEPA・DHAなどのオメガ3脂肪酸が豊富で、抗炎症作用や中性脂肪低下効果があります。
赤身肉には鉄分・ビタミンB群が多く、疲労回復にも役立ちます。
今日から始められる実践ステップ
- 毎食に必ず魚または肉を一品入れる
朝はサバ缶や鶏むねハム、昼夜は焼き魚・ステーキ・蒸し鶏などシンプル調理でOK。 - 脂質は調理法でコントロール
揚げ物よりも、蒸す・焼く・煮るを優先。油を使う場合はオリーブオイルやごま油を少量。 - 炭水化物は「動く前に」
トレーニング前後や活動量が多い時間帯に摂取し、夜は控えめにする。 - 水分を十分に取る
タンパク質代謝には水が必要。体重 × 30mlを目安に。
ダイエットにおすすめの魚
ダイエット経験者なら一度は「鶏むね肉最強説」を耳にしたことがあると思いますが、実は魚も負けてはいません。
むしろ、魚には肉にはない脂質の質の良さとミネラルの豊富さがあり、年齢を重ねた体にはより有効です。
30〜50歳の体は、炎症・血中脂質の上昇・ホルモンバランスの変化などが起こりやすく、魚に含まれるEPA・DHAはそれらの改善に大きく貢献します。
ここでは、白身魚・青魚それぞれの特徴と、ダイエット中に特におすすめの魚を紹介します。
白身魚(タラ・ヒラメ・カレイ)

白身魚は、低脂質・高たんぱく・消化に優しいのが最大の特徴です。
特にダイエット後半でカロリーを絞りたい時や、胃腸が疲れている時に最適。
栄養面のメリット
- 脂質は100gあたり1〜3gと非常に低い
- ビタミンB12やリンなどのミネラルが豊富
- タンパク質含有量は20g前後と肉類に匹敵
調理のポイント
- 蒸す・煮る調理で脂質ゼロに近づける
- 塩麹や酒で下味をつけてしっとり感をキープ
- 冷凍切り身をストックすると時短になる
おすすめ料理例:
- タラの蒸し焼き(ポン酢+ネギ)
- カレイの煮付け(砂糖控えめ)
- ヒラメの昆布締め(刺身で高たんぱく低カロリー)
青魚(サバ・サンマ・イワシ)

青魚は「脂が多いからダイエット向きじゃない」と思われがちですが、それは大きな誤解。
青魚の脂はオメガ3脂肪酸(EPA・DHA)で、これは中性脂肪を減らし、血液をサラサラにする効果があります。
栄養面のメリット
- EPAが炎症を抑え、脂肪燃焼をサポート
- DHAが脳の働きを助け、集中力アップ
- 良質な脂質が満腹感を持続
調理のポイント
- 焼き過ぎると脂が流出するので中火〜弱火で
- 水煮缶を活用すれば調理ゼロで高栄養
- 塩分は控えめに(缶詰は湯通しで減塩可能)
おすすめ料理例:
- サバの塩焼き+大根おろし
- イワシの梅煮(砂糖はラカントに置き換え)
- サンマの塩焼き(内臓もEPAが多い)
高たんぱく低脂質の魚ベスト5
- マグロ(赤身):タンパク質26g、脂質1g
- カツオ:タンパク質25g、脂質1g
- スズキ:タンパク質20g、脂質1g
- タラ:タンパク質17g、脂質0.3g
- ホッケ(干物):タンパク質20g、脂質2g
これらはカロリーを抑えたい時期に特に活躍します。
まとめ
魚はダイエット経験者にとって、肉に偏りがちなタンパク源を補完する強力な武器です。
特に青魚のEPA・DHAは、年齢による代謝低下や血中脂質の上昇に対抗できる成分。
「週3回は魚を食べる」を目標にすると、体脂肪減少だけでなく健康診断の数値改善にもつながります。
ダイエットにおすすめの肉
ダイエットのタンパク源として真っ先に思い浮かぶのは肉。
実際、肉は高たんぱくで満足感も得やすく、調理の幅も広い食材です。
ただし、肉は種類や部位、調理法を間違えると脂質過多になり、せっかくの努力が水の泡になることも。
ここでは、鶏・牛・豚それぞれのメリットと注意点、さらにダイエット経験者が陥りやすい「肉の落とし穴」も含めて解説します。
鶏胸肉とささみの使い分け
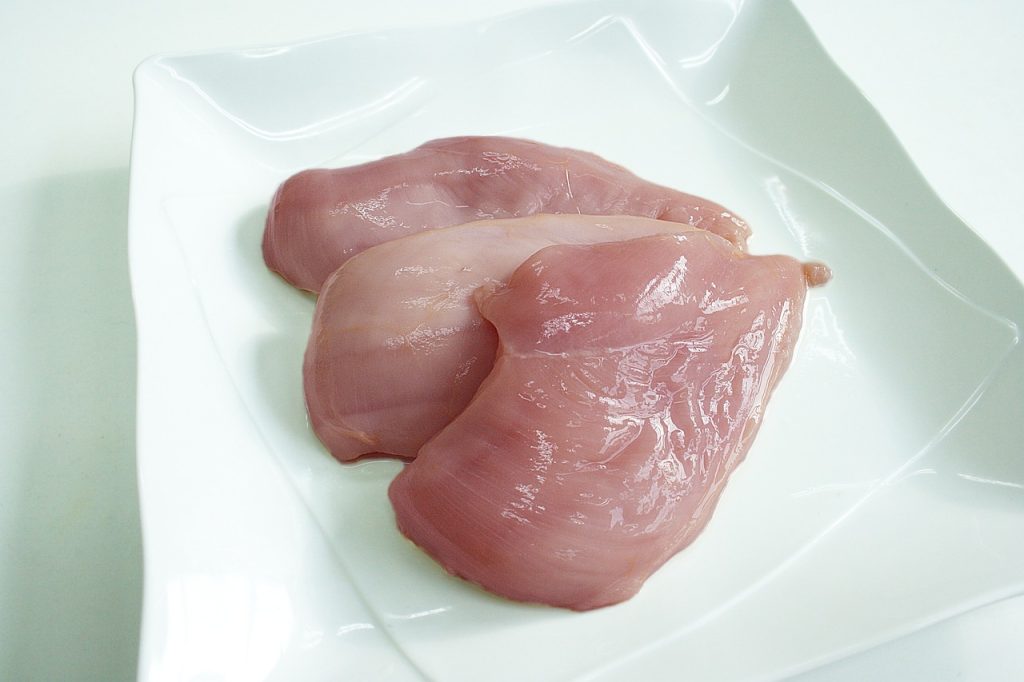
鶏胸肉の特徴
- 100gあたりタンパク質約22g、脂質約1.5g(皮なし)
- イミダペプチドという疲労回復成分を含む
- 値段が安く、調理法も豊富
ささみの特徴
- 100gあたりタンパク質約24g、脂質約0.8g
- 胸肉よりさらに低脂質
- 小ぶりで火が通りやすく、時短向き
使い分けのポイント
- 胸肉はメインディッシュに(蒸し鶏・グリル・低温調理)
- ささみはサラダ・スープ・和え物に(コンビニでも手に入る)
赤身肉(牛・豚)

赤身肉は「脂質が多くて太る」と思われがちですが、部位を選べばダイエット向きです。
メリット
- 鉄分・亜鉛・ビタミンB群が豊富(特にB12)
- クレアチンが筋力維持に役立つ
- 噛みごたえがあり、満腹感が得やすい
注意点
- 部位によっては脂質が高い(霜降りは避ける)
- 調理油の使いすぎに注意
おすすめ部位(100gあたりの脂質)
- 牛ヒレ:脂質5g
- 牛モモ:脂質7g
- 豚ヒレ:脂質3g
- 豚モモ:脂質5g
加工肉の落とし穴(ソーセージ・ハム)

加工肉は手軽でおいしい反面、
- 添加物(リン酸塩・発色剤)が多い
- 脂質と塩分が高め
- タンパク質量のわりにカロリーが高い
結論:ダイエット中は常用せず、非常時や外出先の非常食として限定的に使う。
まとめ
肉はダイエット経験者にとって欠かせない食材ですが、選び方と調理法次第で結果は大きく変わります。
鶏胸肉や赤身肉を中心に、脂質と塩分をコントロールしながら摂取すれば、脂肪燃焼と筋肉維持の両立が可能です。
本日の著者
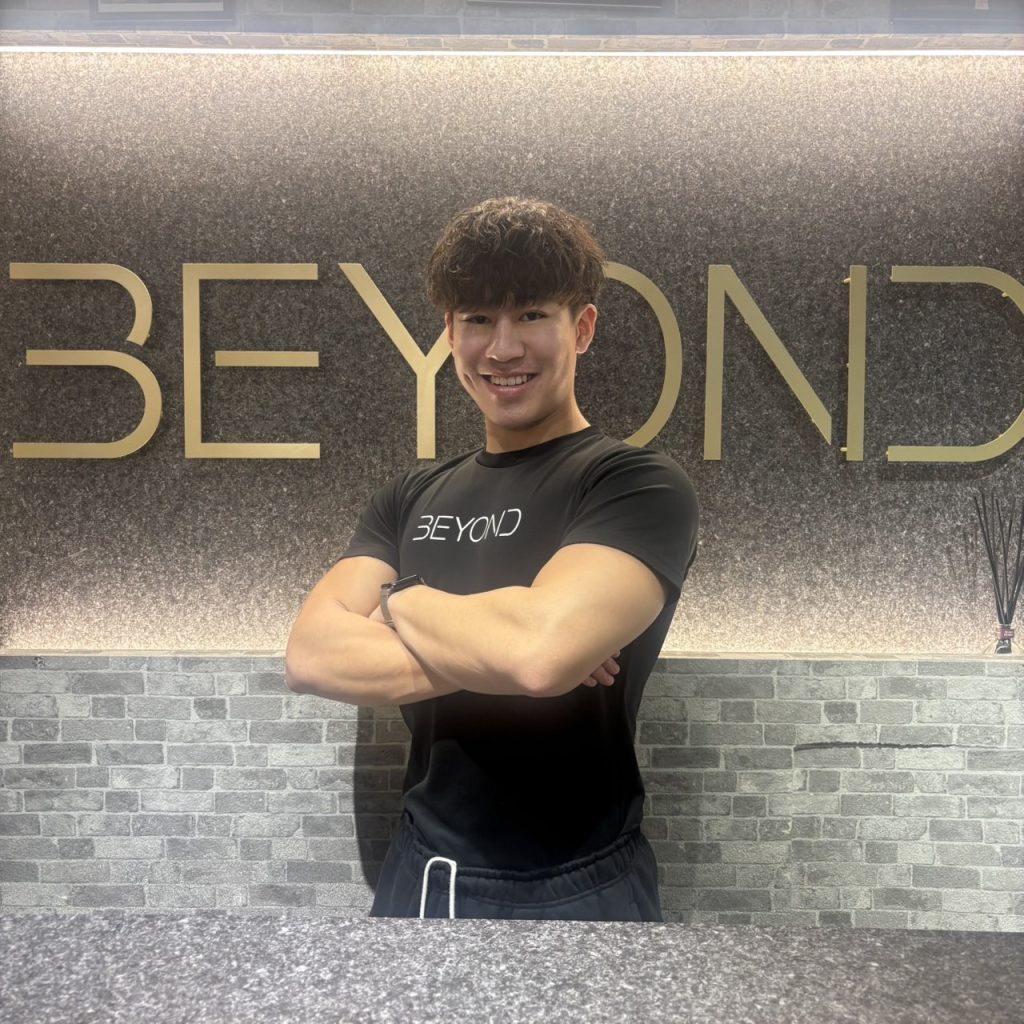
○名前 糸井 元哉 (いとい もとや)
○趣味:都内のお洒落カフェ巡り
○実績
2024 APF GUARDNER BELT CUP クラシックサーフ部門 3位
店舗詳細

- パーソナルジムBEYOND 溝の口店
- 神奈川県川崎市高津区溝口2-14-31 MSメディカルビル6A
- 営業時間 8:00~23:00
- 電話番号 044-811-0810
パーソナルジムに通うべきか迷っている方へ──
「効果はどれくらい続ければ出るの?」「いつまで続けるのがベスト?」そんな疑問にお応えします。
パーソナルジムは、短期間のダイエット目的から、長期的なボディメイクや健康維持まで、目的に応じて柔軟に通い方を選べます。
特に「確実に結果を出したい」「運動初心者で続けられるか不安」といった方には、食事指導や正しいフォームを学べるパーソナル指導が効果的です。
まずは体験にお越しいただき、自分に合った継続期間や通い方を見つけましょう。
BEYOND溝の口店では、あなたの目標に寄り添った最適なプランをご提案いたします。